「育休を取りたいけど、収入がどうなるか心配…」「家計が回るのか不安…」そんなお金の悩みで育休をためらっている男性は少なくありません。この記事では、男性が育休を取得する際に知っておきたいお金にまつわる制度や賢いハック術を、育休経験者の視点でリアルに解説します!
1. 育児休業給付金の仕組みと計算方法
1-1. 育休中の給付金、どれくらいもらえる?
育児休業中、最も重要なのが「育児休業給付金」。これは雇用保険から支給されるもので、育休開始から180日(およそ6か月)は休業前の賃金の67%、それ以降は50%が支給されます。
例えば、月収30万円の方であれば、6か月間は月20万1千円、7か月目からは15万円の給付というイメージです。給付金には所得税はかからず、住民税の課税対象にも原則含まれません(給付金は非課税所得として扱われるため)。ただし、住民税への影響は翌年の課税額に反映されるため、実際に恩恵を感じられるのは翌年度からになります、手取りベースでは実際の給与の7〜8割に近くなるケースもあります。
なお、育児休業給付金には「上限額」があり、2024年度時点で、支給額は月額上限:
- 約314,991円(67%時)
- 約234,420円(50%時) となっています。高収入の方は上限に引っかかり、実質の給付割合が下がる可能性があるため注意が必要です。
1-2. 給付金の支給条件と申請手続き
育児休業給付金の支給には以下の条件があります:
- 雇用保険に1年以上加入している
- 育休開始日から8週間ごとに会社を通じて申請する
申請は通常、会社の人事部が対応してくれますが、自分でも手続きの流れを確認しておくと安心です。ハローワークに必要書類を提出する形となり、会社と密に連携することが重要です。
1-2-1. 支給開始は早くて2か月後!タイムラグに注意
育児休業給付金は「育休を開始したから即もらえる」というわけではありません。実際の支給には、初回申請から約2〜3か月ほどのタイムラグが発生することが一般的です(体感として3か月以上かかったという声も多く聞かれます)。
なぜ時間がかかる?
- 書類のやりとりが会社・ハローワーク間で必要
- 初回申請は「2か月分をまとめて申請」が原則
- ハローワークの審査や振込に時間がかかる
さらに、配偶者(妻)が育児休業に入る場合は、産後休業(通常は出産翌日から8週間)が終了してから育児休業が開始されるため、申請や支給のタイミングもその分後ろ倒しになります。結果として、支給まで3か月以上かかることも珍しくありません。
備えはどうする?
- 育休開始までに生活費2〜3か月分の貯蓄があると安心
- 家賃やローンなどの引き落としスケジュールを再確認
- 配偶者の収入や手当(出産手当金など)を含めてキャッシュフローを試算
育児というビッグイベントのスタートを慌てず迎えるためにも、この“給付金空白期間”はぜひ意識して準備しておきましょう。
1-3. 育休開始・復帰のタイミングを工夫しよう
育休をいつ開始し、いつ復帰するかによって「社会保険料」に大きな差が生まれること、ご存じですか?実は育休の初日や復帰日は、戦略的に設定することで数万円単位で家計に優しい結果をもたらします。
育休開始は“月初の休日”がベスト
育児休業に入ると、一定の条件を満たせばその月の社会保険料(健康保険・厚生年金)が全額免除になります。ポイントは以下の2点:
- 育休の初日が「その月の最初の出勤日前」であること
- その月の全日が育休であること
この条件を満たすには、できれば「月の初日が土日祝日」である月を狙い、1日から育休に入るのがベスト。たとえば月曜日が1日なら、その前日の「日曜=休日」から育休を取得すると、最も無駄がありません。
復職は“月末を避けて翌月に”が鉄則
社会保険料は「1日でも働けばその月の保険料が満額発生する」という特徴があります。そのため、育休明けの復職日が月末に近いと、数日働いただけで1か月分の社会保険料を支払うことに…!
可能であれば、復職は「翌月の1日」「週明けの月曜日」に設定することで、保険料を無駄にせず済みます。特に月末が金曜日などの場合は、土日を挟んで週明け復職が理想です。
ボーナス支給前に育休に入る裏技も
ボーナスに対しても社会保険料がかかりますが、育休中であれば「支給対象外」としてボーナスに保険料がかからないケースも。会社の規定や支給基準日によるため、事前に人事・給与担当に確認しておくのが重要です。
▼図解:育休開始日と社会保険料の発生有無
| 育休開始日 | 月初が平日 | 月初が休日(例:日曜) | 保険料の発生 |
|---|---|---|---|
| 1日(平日)開始 | 保険料発生の可能性あり | ○(免除対象) | △条件次第 |
| 1日(休日)開始 | ○(免除対象) | ◎(ベスト) | ◎免除確実 |
| 月中(10日など) | ×(一部期間労働扱い) | × | ×保険料発生 |
※詳細は事業所の就業規則や締め日による違いあり
2. 社会保険料がゼロに!?隠れたメリットとは
2-1. 健康保険・厚生年金の保険料免除制度
育休中は、なんと健康保険と厚生年金の保険料が免除されます(会社が申請すればOK)。免除される期間中も、保険加入は継続されている扱いなので、将来の年金額や医療保険の受給に影響はありません。「保険料ゼロで保障アリ」は、かなりのお得ポイントです。
2-2. 住民税・所得税への影響
育休中は給与収入が減るため、翌年の住民税額も下がります。また、給付金自体には課税されないため、節税効果も大きいです。年末調整や確定申告の際に損をしないよう、手元の明細をしっかり保管しておきましょう。
3. 手取りを減らさない育休ハック
3-1. 夫婦の育休タイミングをずらす
パパとママの育休をずらして取得することで、家庭の収入源を完全にゼロにせずに済みます。例えば、ママが出産後すぐ育休を取得し、パパはその後のタイミングで交代制のように育休を取ることで、給付金が効率的に支給されます。
3-2. 家計を見直す“育休予算”のススメ
育休中は一時的に収入が減ることを前提に、妊娠中から「育休予算表」を作るのがオススメ。家計簿アプリで固定費と変動費を仕分けし、「この支出はなくせる?」「今のうちに貯めるべき額は?」などを夫婦で話し合っておくと安心です。
3-3. 出産・育児に使える助成制度をフル活用!
- 出産育児一時金(約50万円)
- 児童手当(月1〜1.5万円)
- 自治体の独自支援(紙おむつ券、育児用品補助など)
こうした支援制度を調べて、もらい忘れがないようにチェックリストを作っておくとベストです。
4. 実際どうだった?我が家のお金事情
4-1. 我が家のリアル収支
私のケースでは、1人目の時は外出も減って支出も減ったのでギリギリ収支はマイナスにはならなかったです。奥さんが異常に温度管理を気にするので、冬場や夏場は電気代がエグかったです(前年比3倍とかになりました)オムツ代、ミルク代で児童手当はほぼ消えます。
あとは月の固定費部分を削りました。奥さんのクレジットの明細を見るとよく分からんサブスクが出てくる出てくる。。。。
ついでに家計の見直しも進みました。
4-2. 節約だけじゃない!育休中の副収入
実は育休中に、ブログを始めたのがきっかけでちょこちょこ副収入も発生。ガッツリ稼ぐのはNG(給付金停止の可能性アリ)ですが、月1〜2万円程度なら黙認されるケースも多いです(念のため会社と相談を)。
5. 男性育休×お金、まとめとアドバイス
育休中の不安で一番多いのが「お金」。しかし制度をしっかり知れば、実質の手取りは思ったほど減らないし、各種支援や免除制度もかなり手厚いです。
育休は「稼がない時間」ではなく、「家族に投資する時間」。 手取りが減っても、子どもとの時間や家庭の充実度はプライスレス。
・給付金と社会保険免除で手取り7〜8割確保 ・育休開始日は“休日”、復帰は“週明け”が鉄則 ・ボーナス時期を狙えば、社会保険料の節約も可能 ・制度活用で「経済的損失ゼロ」に近づける
不安があれば、まずは人事に相談。そして、育休を取った先輩パパの話を聞いてみましょう。きっとあなたの背中を押してくれるはずです。
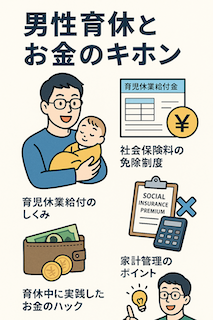
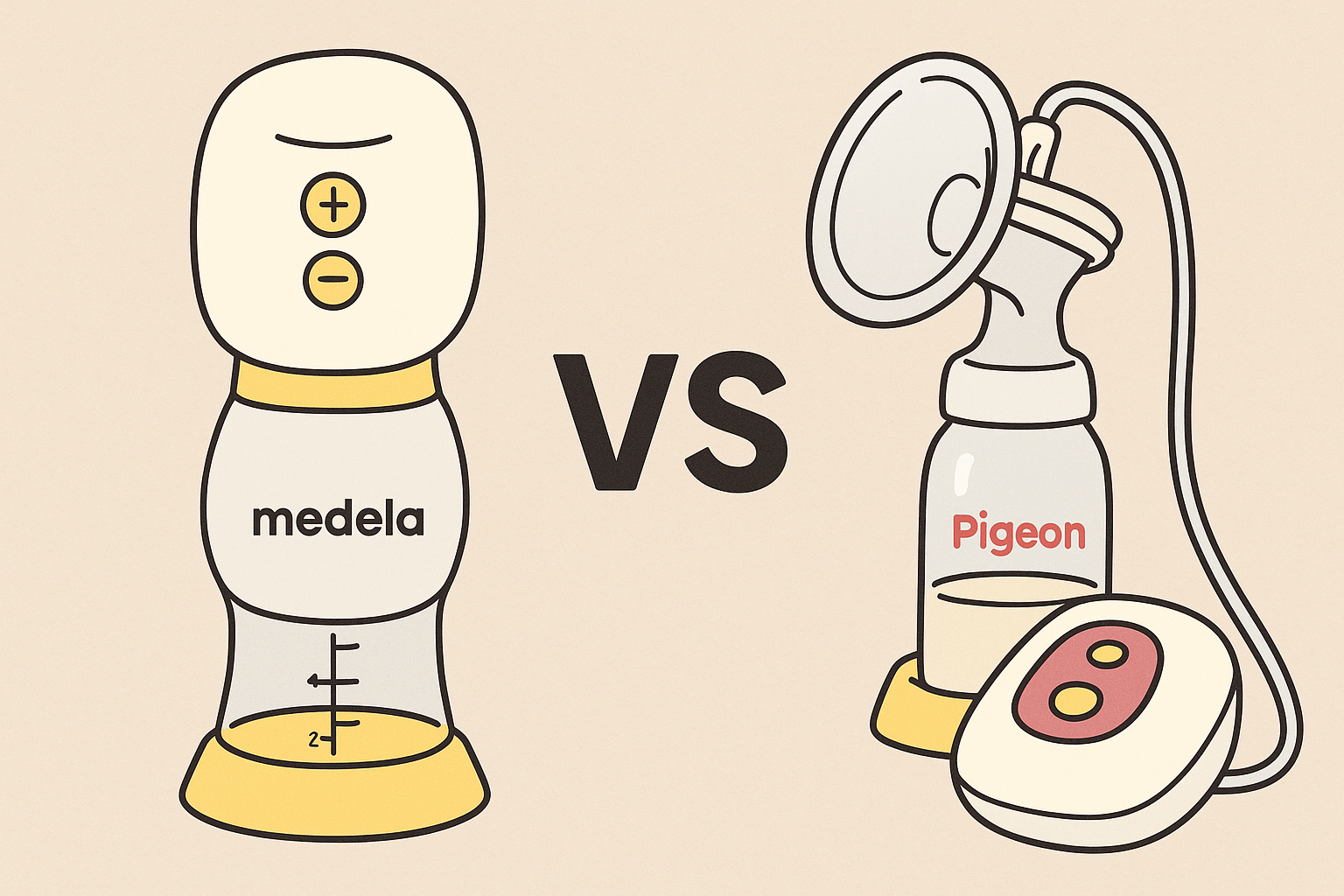
コメント